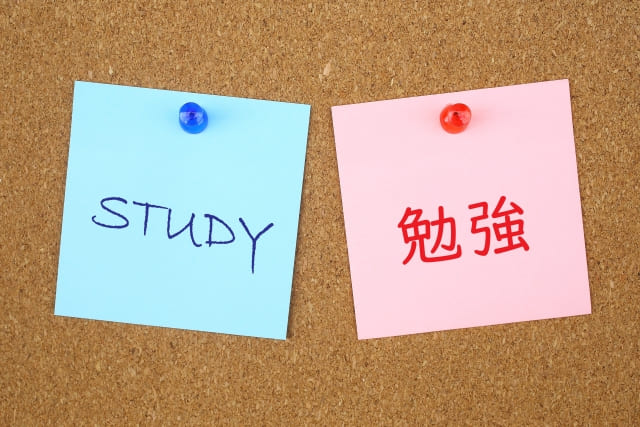こんにちは。
「英語を話せるようになりたい」
「バイリンガルになりたい」
という中学・高校生とその保護者の方を全力で応援するブログです。
冒頭の「ことばが人生を作る」という一文。
いろんな成功者の方々が「自分が発する言葉が重要だ」と言ってます。とてもとても大切な教訓。
わたしも自分が使う言葉はなるべく気を付けてます。言葉が自分の人生を形作るわけですから。
でも今回書きたいのは人生論的なことではなく、
英語と日本語の【文法構造】の違いが、「欧米人」の性格と「日本人」の性格との違いにも表れている
のではないかということです。
「ことばがあなたの人生を創る」…英語/英会話を学ぶ【中学生】は知っておいて
“I am —.”

” I am ~ .
“英語で「わたしは・・・」
というとき、 “I am ~ . ” で表します。
この “ I ” は、いつでもどこでも必ず大文字です。
文章の「出だし」だろうが「中盤」だろうが「最後」だろうが、必ず大文字。
かたくなに大文字。
書くのが楽と言えば楽。たて棒一本引くだけ。
ちなみに他の人称代名詞(You, He, She, Theyなど)は、文の途中では小文字になります(you, he, she, theyなど)。
でも「わたしは・・・」だけは、文のどこに出てこようと、必ず大文字の “ I ” です。
Capital letter。
例えば
「私は、彼がくれた時計を身に着けている」の場合、
” I am wearing the watch which he gave me.”
となります。
ここで “He” は、”he” に、なります。小文字です。小さくちぢこまってます。
ここで上の文章をひっくり返してみます。
「彼は、わたしがあげた時計を身に着けている」の場合、
“He is wearing the watch which I gave him.”
なぜか小文字の ” i ” ではなく、” I “になってます!
大文字になってます。
ちなみにこの文の「主語」は 、”He”「彼は」、です。
主語の「主」は、主人の「主」、あるじの「主」、主役の「主」。
上記の文の「主」役は “He”なのに、
「彼は俺様があげた時計を身に着けてる」と言わんばりの主張の強さ。
もう一度ひっくり返してみてみましょう。
“I am wearing the watch which he gave me.” の場合
“he”は、ちゃんと自分をわきまえてます。小文字におさまってます。主語、つまり主役の “I” より目立とうとはしていない。
さらにびっくりすることに
“He plays soccer better than I do.” 「彼は私よりサッカーが上手です」の文章。
「彼の方が上手だ」と彼を称賛しておきながら、
“than I” (俺様より)
と言ってる!
“than i “と、小文字のテンションで、遠慮がちに言うのが、文化的なジャパニーズスタンダード。
でも「私は」の “ I ” はいつでも、どこでも、何が起きても、大文字。
これがイングリッシュスタンダード。
カルチャーショックというかラングエッジショック。
「自己主張」の強さは、自立心や独立心ともつながってるから、マイナスばかりじゃない。
世間を生きてく上で大切な「自己肯定感」にもつながる。これはあった方が絶対いい。
いつでもどこでも、
「わたしは」何者か、
「わたしは」何をするか、
「わたしは」誰とつながりたいか、
が大事なのだと英語の神様は言っているのかもしれない。
欧米人の、時に「両刃の剣」となってしまう自己主張の強さが、これに表れているような気がします。
日本語の主語
日本語だとどうでしょう。
例えば
“I am hungry.”
という文をわれわれが言うとき、よほどのことがない限り
「腹減った!」というのではないでしょうか。
「わたしは腹が減った!」
なんて言うのはかなり状況が限られると思います。
ほかにも、疲れて帰って来て言う
” I am tired!”
も、「わたしは疲れたあ!」というよりも、「疲れたあ!」という日本人がほとんどではないでしょうか。
日本語は、
「わざわざ言わなくてもわかるだろう」
って感じの主語は、しょっちゅう省略されますよね。
だって「腹が減ってる」のも、「疲れてる」のも、本人が感じてるんだから。
本人が感じてるから言ってるんでしょ!って。
初めてアメリカに行った頃に、「日本語をそのまま英語にしても、なかなか会話がつながっていかない!」と感じましたが、原因の一つはこの「主語」の違いが根っこにあるからなのかもなあ。
日本語は「主語」をしょっちゅう省略する。
だから、省略された部分を「察する」必要が出てくるんですね。「空気を読む」必要が出てきちゃう。
様々な一人称
さらに日本語には
英語の “ I “にあたることばに、
私、
僕、
俺、
オイラ、
手前、
小生、
うち
などたくさんあります。
ほかにも
デーモン小暮は「吾輩(わがはい)」だし、時代劇では「拙者(せっしゃ)」や「某(それがし)」なども使われてます。
以前見た映画では、劇中の天皇陛下が「朕(ちん)」って言ってた。
こんな感じで、日本語では自分で自分を呼ぶための一人称がたくさん在ります。
英語で自分を言う時は、
必ず ” I ” です。
絶対に変わらない。
男の子が「僕」で女の子が「わたし」なんて違いはないです。
いつでも、どこでも、何が起きても
“ I ” 。
英語の方が「ぶれない自分軸」があるってことなんでしょうか??
いやいやそうとも限らない。日本語にも優れた点はたくさんあるはず。
「主語」がしょっちゅう省略されるのも、一人称がたくさん種類があるのも、「自分」よりも「みんな」や「一体感」を大切にする日本人の魂がことばにも表れているんだと思います。
自分が言いたいことよりも、周りの空気を読むことを優先する。それが「息苦しい」と感じる人は少なくないはず。わたしも昔はそうでした。
でもこれってマイナスばかりではない。
みんなで力を合わせないと乗り越えられない状況では、チームワークが最大の武器になる。
東日本大震災のときに世界が称賛したのは、困難な状況下にあっても他者を思いやれる優しさだったはず。
反対にアメリカで何年か前にハリケーン・カトリーナがルイジアナ州を襲って壊滅状態のとき、窓ガラスが割れたスーパーの中に人が流れ込み、日用品や食料をわれ先にと奪い合っていた。
災害が襲ってただでさえ大変な状況のなかで、「暴力」や「略奪」が起きてた。
日本人は、日本語は、やっぱり素晴らしい、と思いたい。
結論。
ということで、わたしは
【日本語】と
【英語】の
両方「いいとこ取り」をしたい!
というのが私の結論です。
「ぶれない自分軸」と「周りと協力する力」のいいとこどり。
“1+1=2” ではなく、
“1+1=3 とか4 “、
になることを信じて
これからもっともっと精進します。
他にも、英語をマスターするには【語順】の違いを知ろう、という記事もあるので、そちらも読んでみてください。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
記事執筆者:上田卓史
英語・英会話講師
中学・高校生むけ英語・英会話:ことばの両利き舎代表