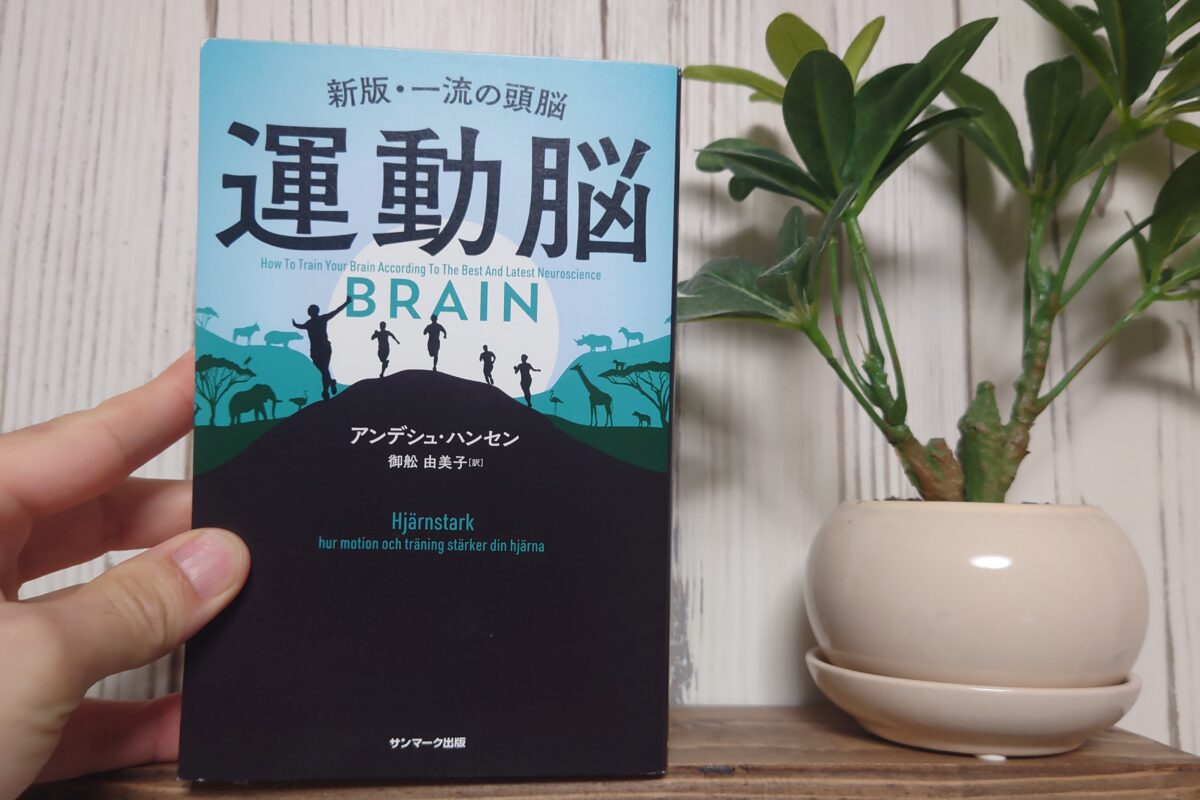こんにちは。
本記事は、スウェーデン人の精神科医であるアンデシュ・ハンセン氏が書いた
「運動脳」
という本を参考に、
勉強に一生懸命な「中学生・高校生」には、ぜひ運動を習慣にして、勉強効率を最大化して欲しい
をというお話をします。参考になれば幸いです。
勉強をがんばる中学生・高校生にとって「勉強法」より大切なこと_アンデシュ・ハンセン著『運動脳』を読んで
目次
テクニックの前に「強靭(きょうじん)な足腰」
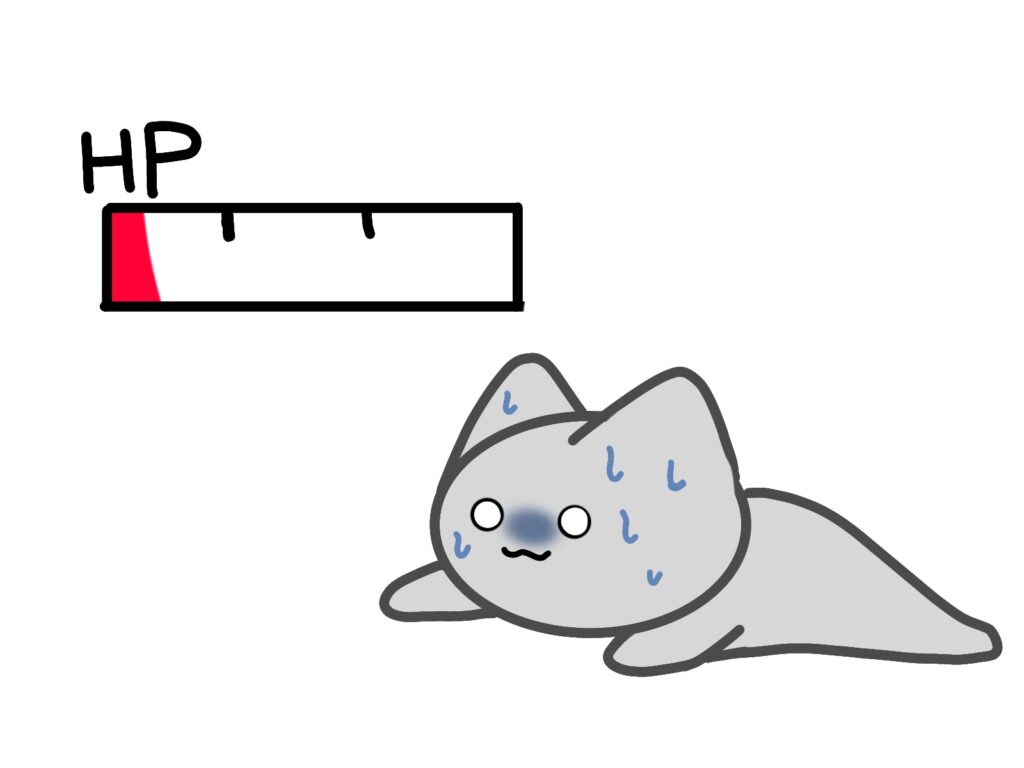
あなたがサッカーやバスケなどのスポーツで活躍したい場合、ドリブルやパス、そしてシュートなどの技術を磨くでしょう。つまり「テクニック」です。
でも、それは「体力」や「強靭な足腰」があってこそ。3,4分動いたらもうヨレヨレになるようでは、試合で思い通りに動けません。足はヨレヨレ、息は苦しくてゼーハー...これではせっかくの「テクニック」も全く使えません。
「勉強」にも同じことが言えます!
世の中に勉強法は数多くありますが、それは「テクニック」です。そしてスポーツにおいての「体力」や「強靭な足腰」にあたるのが「運動脳」です。
「運動脳」とは、
- 脳の働きの良し悪しは身体活動や運動で決まる。身体活動や運動を習慣的にすることで初めて脳はその働きを十分に発揮できる。
ということ。
つまり、あなたが勉強する際に、その勉強の効率を最大に高めて、より良い結果につなげるには、習慣的に身体を動かすこと(運動)は欠かせないということです。
もうこれが本記事の結論です。
さらに著者の言葉を引用すると、
身体を動かせば、たちまち心と身体が健康になり、脳の働きもよくなる。そして運動を習慣にして長く続けるほど、その効果のすばらしさが実感できるだろう。
352ページ アンデシュ・ハンセン『運動脳』
ということです。
もちろん、テクニックである「勉強法」は必要だし大事です。
でも、【優先順位】が高いのは、
『運動』を習慣化する
ことだと知っておいてください。
勉強する時間を削ってでも運動にあてる方が良い

先ほど出てきた、本記事の結論をくり返します。
- あなたが勉強の効率を最大に高めて、より良い結果につなげるには、習慣的に身体を動かすこと(運動)が欠かせない
ということ。
以下に『運動脳』で述べられていた大切なポイントを挙げます。
- 運動以上に記憶力を高められるものはない
- 脳がしっかり働くためには、脳だけでなく身体も合わせて使う
- 脳が「あなた」をコントロールしているのでなく、「あなた」が脳をコントロールしている
- 運動は不安・ストレスを鎮めるのに最も効果的
- 運動は集中力や注意力が高まる
- 集中力の高い・低いは遺伝子や環境でなく、あなたの生活習慣で決まる
- 身体を動かさないと、思考が遅くなり、判断が鈍るし、うつ・不安にもなりやすい
- 運動は「創造力」を高め、よい「ひらめき」が多くなる
- 疲れ切ってしまうほど運動する必要はない
- 立って勉強すると、脳が効率よく働く
- 「筋トレ」よりも「有酸素運動(歩く・走る)」が効果的
- 運動がこどもたちの「読み・書き・計算」の力を伸ばす
など。
まだまだありますが、ざっと挙げるとこんな感じ。
またまた著者の言葉を引用します。
子どもの記憶力や学習能力を驚異的に伸ばす方法として科学の研究が立証したもの、つまり身体活動にこそ注目すべきなのだ。スウェーデンにかぎらず、現代の子どもたちは決して充分に身体を動かしているとはいえない。
282ページ アンデシュ・ハンセン『運動脳』
身体活動には集中力が増す、気持ちが晴れやかになる、不安やストレスが減る、記憶力が向上する、創造性が増す、知能が高まる、といった多くのメリットがあることをご理解いただけたと思う。
329ページ アンデシュ・ハンセン『運動脳』
メリットは無数にあって副作用はなし。
まさに、「百利あって一害なし」です。(「百害あって一利なし」ということわざを勝手にひっくりかえしてみました。)
周りと比較しない!体育や部活動での注意点

「体育は大キライなんだよな」とか、
「運動とか体をうごかすのは大の苦手」とか、
そう思ったあなたに知っておいてほしいのは、
【運動が得意になる必要は全くない】
ということ。そして、
【他人と自分を比較しない】
ということです。
著者の言葉を引用します。
運動といっても、何かの選手になったり、腹筋が6つに割れるまでトレーニングをしたりしなくてもいいのだ。要するに、これは脳が存分に性能を発揮できるようコンディションを整えようという話なのである。
352ページ アンデシュ・ハンセン『運動脳』
学校生活は、否応なしに周りの人との比較にさらされますよね。「体育」の授業や「部活動」なんかでは特に。
運動神経がいい人と自分を比べてしまって「自分はダメ」みたいに自分を否定をしてしまうかもしれません。
または、部活でレギュラーになった友人と自分を比べて、ベンチにいる自分は「どうせ何やってもダメだから」と、投げやりになったしまったり。
私は、こどものころ水泳が苦手で、プールの授業で周りがキャッキャッ言って盛り上がってるのを見ながら、自分はただ水中で必死にもがくだけの授業が苦痛でした。
でも!
ここで話している「勉強の効率をあげるため」の運動では、【他人との比較】は全く意味がありません。
いや、むしろ害になるかも。
あなたが目指すべきは、自己ベストの更新です。
しかも、ここで言う自己ベストとは「50mを~秒で走れた!」のようなものではなく、
「今日3分ランニングできたから、次回は5分を目指そう」とか、
「今週は3回ウォーキングしたから、来週は4回を目指そう」とか、
「1日おきに軽い運動をして、それを1か月続けよう」とか、
小さな行動をどれだけ積み重ねることができたか
の自己ベストです。
あくまでもこの「小さな行動」の継続についての自己ベストだけを考えてください。
勉強と運動の「バランス」が大事
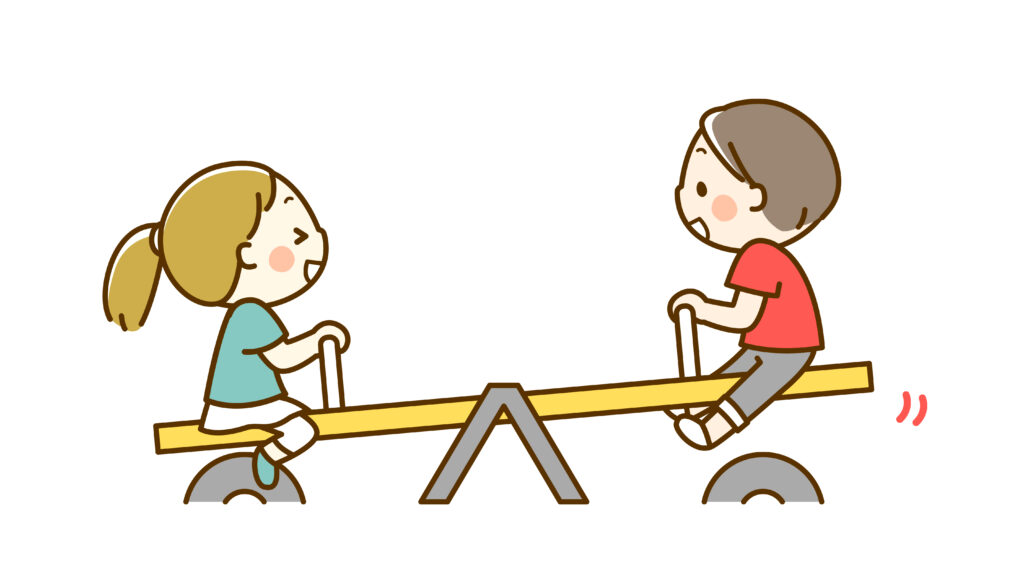
もしあなたが、全く勉強時間を確保せず、理解や暗記をするための努力を全くしようとせずに、「ただ」運動をし続けたとしても効果はうすくなってしまいます。
もしあなたが、普段から活動的に体を動かしているのであれば、
運動の時間を少し減らして、勉強する時間を増やす
ことをしてください。
反対に、
「勉強時間は十分とっている」けど、
運動はほとんどしていない
座っている時間や寝転がっている時間が長い
という人は、ぜひ
1日10分でも20分でもいいから、歩く時間、軽く走る時間をとる
ことをしてください。
少しの運動で大きな効果が得られるはずです。そして、それを習慣にできれば、勉強法という「テクニック」が、さらに効果的に使えるようになるでしょう。
「運動」と「勉強」の、どちらか一方に偏ることなく、二つのバランスをとることが大事だと肝に銘じてください!
「やらされるからやる」ではなく「自分からやる」
「体育」や「部活動」では、自分から「よし、やるぞ!」と動き出さなくても、「やらされる」でしょう。もちろんそれでも「何もしない」よりは何倍もマシです。
でも、あなたにぜひ覚えておいて欲しいことがあります。それは、
【脳は、人から強制的にやらされるよりも、自分から自発的に動く方が10倍も吸収力が高まる】
という事です。(参考:KIDSNA STYLE 「やりたい!」が脳を10倍 活性化させる_脳研究者 池谷 裕二)
「なんでこんなことやんなきゃいけねーんだ」
「バカらしい...」
「めんどくせー」
という態度で運動をするよりも、
『自分は遊びの時間を削って勉強している。せっかく貴重な時間を使って勉強してるのだから、無駄な努力はしたくない。ぜったいに成果を出したい。そのために『運動』を習慣にする。自分のためにやる。』
という態度でのぞむ方が、結果に10倍の差が出るということです。
ぜひ、受け身の態度は今日限り捨てて、自ら能動的に動くクセをみにつけてください。
最後に~社会に出てからも「運動」を習慣にして

学校にいるときは、嫌でも体育の授業で身体を動かす機会があります。でも、社会に出てしまうと、その機会はなくなります。
つまり、自分で「運動」をする機会を作り出さないといけません。
さらに、それを「習慣」にする工夫もしなければなりません。
...大変です!
でも、ここまで述べてきたように、
あなたの健康や学力、仕事での充実感や心の豊かさと「運動習慣」とは、切っても切れない関係です。同じコインの表と裏ということ。
あなたが将来、望む人生を送りたいのであれば、この「運動習慣」をどうか生活の中に取り入れてください。
たまに忙しくなって運動できなくなってたとしても、大丈夫!またしばらくして落ち着いたら始めればいいのです。
100点満点でなく「65点」でOK!
小さな行動を積み重ねる、継続する!
ことです。
また、人からやらされるのでなく「自分」で決めて自分で動きましょう。友人などを誘っていっしょにやるのも良いですし、サークルなどに入るの良いでしょう。
ちなみに...
「たった・・・だけで劇的に」
「奇跡の...」
のようなうたい文句の商品やサービスに惑わされないように注意してください。簡単に手に入るものは、簡単に去っていくか、または副作用がおおきいかのどちらかです。
最後に著者の言葉を引用します。
脳トレのアプリは、いまや数十億ドルもの巨額の利益を生んでいる。だが、それは忘れていい。効果はないからだ。脳に目覚ましい効果があると謳(うた)うサプリメントや種々の「奇跡のメソッド」も無視していい。これも、やはり効果はない。
352ページ アンデシュ・ハンセン『運動脳』
ここまで読んで頂きありがとうございました。
記事を読み終えて「ピン」と来た人は、ぜひ実際に著書を読んでみてください。必ず得られるものがあるはずです。
『運動脳』_著者:アンデシュ・ハンセン
記事執筆者:上田卓史
教室HP:中学・高校生の英語・英会話|新潟
教室ツイッター:https://twitter.com/ryokikisha
動画教材:https://www.youtube.com/@user-ex9wz7yt8m